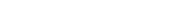21AW STORY
WHITE LIE
脚本:dilemma
小説:藤田祥平
祖母の車椅子を押して冬の庭を歩いた。そうしているうちは元気そうだった。この梅は陽がよくあたるから早く芽が出そうだねと、細かいところまで見ているので感心した。
寒かったが、空気は初春の気配をもっていた。いつまでも歩いていられそうに思われた。しかし祖母の身体が冷えた。
玲二は病院の庭から祖母の病室に戻った。看護師たちとともに、ベッドに祖母の身体をのせた。
「あんまりいい部屋で、勿体ないわ。最近の病院はホテルみたいなのね」
祖母の微笑みに、もう私はいなくなるのだから、こんな贅沢はほんとうはいらないのだと、はっきり書いてあった。
玲二はスツールに腰掛けて、身体を祖母のほうに傾けて、小さな声で笑った。膝のところで手を組み、すこしうつむいた、悲しみと喜びが入り交じった顔だった。
「その仕草、お祖父さんにそっくりよ」と祖母は言った。
玲二は立ち上がり、掌を額にあてて、病室の窓際に近づいた。
病院の建物と、午後の光に照らされた庭が見えた。
祖母の病室に通ううちに、日本に帰ってきたことの偶然を感じた。もともとは仕事のための帰国で、済み次第戻るつもりだった。しかし実家に着いたとたん、世界中の空港が閉じてしまい、仕事も流れた。
世話になっていたアパートの大家に国際電話をかけると、マンマは――そう呼ぶようにしつけられていたのだが――言った。「扉も窓もみんな閉まってる。こんなナポリは見たことがない」
家賃のこと、残してきた荷物、互いの街の様子などを話したあと、家族の健康に話が及んだ。
「じつは、日本に帰るまで知らなかったんだけれど。祖母が病気なんです」
電話口のむこうではっと息を呑むのがわかった。
「重いの?」
「もう半年、持たないだろうと言われています」
少しの間を置いて、「神様があなたをお遣わしになったのね」とマンマは言った。
「そうだろうか」と玲二は言った。
「お祖母さまによろしく伝えて。クリスチャンじゃないかもしれないけれど、かまわないわ。今日はお祖母さまのために祈ることにする。もう切るわよ。ねえ、お金のことは心配しないで。部屋は誰かに貸すかもしれないけど、荷物は置いておくから」
「ありがとう」
「いつでも電話して」
病状について、医師たちは率直で、看護師たちは話題にしなかった。いずれの職業も必要だった。医師がいなければ話が先に進まないし、看護師がいなければ事実の重さに堪えられない。
食事を運び、シーツを取りかえに来て、おばあさん、お加減はいかがですかと微笑む人々と、苦悩と希望が染みついた表情で、所見をカルテに書き込んでいく、言葉少なな白衣の人々。
たくさんの人がいるので、病院は有機的だった。玲二は内側からそれを撮りたいと思った。仕事でなく写真を撮りたいと思ったのは、久しぶりのことだった。いろいろなひとと話をして、撮影の許可を取り付けた。後押しになったのは看護師たちの声だった。祖母のために繁く通ってくる若者を、看護師たちはよく覚えていた。
「ほんとうに写真家になったのね」カメラを持って病室にあらわれた玲二を見て、ある日に祖母が言った。その日の彼女は、とても辛そうだった。「頑張って、いい写真を撮りなさい」
「もちろん」と玲二は言った。
「でもね、嘘をついちゃだめよ。ごまかしを写しちゃだめよ」
「わかってるよ」
「ほんとうのことを撮るの。そうすれば、ひとの心を動かすものになるから」
不治の病の末期における、家に帰ってもよいという医師の許しは、死に場所を選ぶときが来たという意味にほかならない。そしてその言外の意味は、往々にして、家族ではなく患者のほうがよく理解しているものだ。家族の家でささやかなパーティーが開かれ、ケーキが運ばれた。かつらのうえにパーティー・ハットを被った老女は、ソファに身体をあずけたまま、ワイングラスを手に微笑んでいる玲二や、親戚の子供たちが遊んでいるところを、浅い息をしながら見ていた。夜になって親戚たちが帰ったあと、彼女は布団に入り、そこからあまり出ることがなくなった。
ある夜、祖母は玲二を呼んだ。枕元に近づいて膝を突くと、手のなかに形のくずれたフィルムケースがあった。熱で変形してしまったもののように見えた。
「これを現像してほしいの。お祖父さんとの思い出」
現像のための三種類の薬液を買い直し、簡易な暗室用テントや、フィルムを巻き取るためのリールを荷造りの箱から出してきて、洗面台のそばで準備をした。そのあいだに祖母は、そのフィルムが青垣という場所を写したもので、そこは祖父と祖母の故郷であること、大火災で村が焼け落ちたこと、現像するまえにフィルムが焼けてしまい、どの写真屋も仕事を断ったことを言った。
薬液の配合や温度を調節し、何十年もの昔に撮影されたフィルムの現像作業に入ったとき、彼女の思い出を手術しているみたいだ、と玲二は思った。半分以上が焼けたフィルムを鋏で切り取り、不要な部分を捨てた。それはかつて祖母の一部であったはずなのだが、いまはもう機能しないのだった。
きれいな部分を薬液につけて乾かしてみたとき、手術の失敗を知った。もうずっと以前に手遅れになっていたのだ。現像されたセピアの写真のうち、いちばんまともなものでも、三分の二が白、三分の一が黒で、その境目がおそらく平原――花畑だろうか――と、空の境界であろうと思われるだけの代物だった。ほかには、室内から磨りガラスのむこうに立つ人影を写したものもあり、影はおそらく祖父であろうと思われたが、確言はできなかった。
何十年もの時を越えてきたフィルムの記録が、たったこれだけであるのが虚しかった。
掌のなかの思い出のかけらを見つめたまま、別室の祖母を思い、玲二は迷った。
彼女にこのことを伝えるべきだろうか。
彼女の身体とおなじように、彼女の思い出は手遅れだったのだと、はっきり言うべきなのか。
そうするとして、あまりにも甲斐がないように思われた。
マンマに国際電話をかけた。昼食のあとですこし眠たげにしていたが、話を聞くにつれて、彼女の声はだんだんと真剣になった。
「それじゃあ、お祖母さまの写真の現像は、上手くいかなかったのね」
「そうなんだ」
「なにか知恵はないの」
「ある。彼女の故郷まで行けば、再現したものが撮れるかもしれない。たぶん花畑だから、村の跡に残っているかもしれない」
「いい考えね。でも、それならどうして迷っているの? そちらはロックダウンしていないでしょう?」
「いや。ただ、嘘をついちゃいけないと、彼女に教わったんだ」と玲二は言った。「子供のころから何度も。いい結果を招かないからって」
マンマは十秒きっかり考えてから言った。
「ねえ、写真を嘘にするのは、それを見た人間の解釈と記憶だわ。すべての写真は、それ自体では真実よ」
玲二は微笑んだ。「ナポリの様子はどう?」
「表面上は、なんにも起こらない。『十日物語』どころか、ただの『百日』よ――物語抜きのね。でも、一日の終わり、気の遠くなるような静かな夜に、遠い知り合いが亡くなったと知らせが届く。鎧戸はみんな閉まってる……そのなかに悲しみをいっぱいに貯め込んだまま。もしもあなたがここにいたら、街の写真を撮ったでしょうね」
「詩はできた?」
「いいえ」と彼女は言った。「一行も。スランプね」
翌朝、玲二は言った。
「ばあちゃん。おれ、ちょっと出かけてくるよ」
写真はできたのか、と祖母は控えめに聞いた。
「古いやつだから、時間がかかるんだ。ほんとうはつきっきりでやりたいんだけど、ちょっと外せない仕事があって。夜までには戻って、続きをやるよ。今晩中にはできるから」
玲二が家を出て行ったあと、祖母は夢を見ている。
ここのところ、彼女の現は、夢と区別がつかない。底知れぬ忘却の深みに降りてゆき、失われた記憶を見つけ出すこともしばしばだ。
子供のころ、ひとの親になったとき、恋や仕事や友人たち。たったいま、それらを体験しているみたいだった。なつかしい人々が枕元にあらわれ、行方の知れぬ幼なじみが笑った。
仏様のお呼びが掛かると、夢まで極楽じみてくるのかしらと、彼女は考えた。
今際の際に彼女は、自分の体験が個人的なものではないことを知り始めている。たくさんの夕焼けが忘却のなかで重なって、ひとつの永遠の夕焼けとなるように、いままで生きた日々が重なって、ひとつの永遠のイメージとなりつつあるのだ。
都会の子ではないから、戦争のことは、わからない。あのころは十にもなっていないから、苦しみさえも、いまでは甘い。
しかし、故郷が大火によって焼け、都会へ去ることになったときの感じは、ほかの人間にとっての震災や空襲と、本質的にはおなじであるように思われる。
人間の喜びや、苦しみには、そこまでの種別はないのかもしれない。
こわくない、と彼女は念じる。ひとはみんな、いつか死ぬ。
仕方のないことだ。病気の進みが早すぎた。こんなにもすぐ歩けなくなるとは思っていなかった。気づいたときには駄目だった。
もちろん、運命を変えようとして叶わなかったことは、何度もある。そういうものだと知っていた。人生は、思い通りにいかないことばかりだ。
それでも、見ておけばよかった。この世でたったひとり愛した男が、あのとき微笑みながら撒いた種が、焼け落ちた故郷に芽吹いたのかどうかを。忙しさを言い訳に――彼が永遠に去ったあとは悲しさを言い訳に、見に行こうとしなかった。
現とも夢ともつかない場所に故郷を再現し、二十歳のころのように歩いてみた。
身体は軽く、どこまでも歩いていけそうだった。
想像のなかで、かつて植えられた種が芽吹き、橙色の花びらをつけた。心の中で若く精悍なままの、あの男が植えた花。
いつか帰ってきたときに花々に迎えてもらうために、いま植えるのだと彼は言って、汗をかいて土を拓き、植えていった。
夢のなかで、彼女は彼に声をかけた――「あなたがもうすこし長く生きられたら、花が咲いたかどうか、見に帰ったかもしれないけれど」
すると彼は振り返り、悲しみと喜びの入り交じった表情で微笑んだ。
北陸新幹線が高崎を過ぎて碓氷峠を越えるころ、物思いにふけっていた玲二はスマートフォンを取り出して、ある花の花言葉を調べた。
彼の記憶によれば、それは〈希望〉であるはずだった。
しかし、どの文献を見ても、彼が考えているオレンジ色の花に、〈希望〉の花言葉はあてられていなかった。
玲二は疑問を抱いた。
というのも、彼はかつて、祖母から自分のルーツを聞いたことがある。祖父母の故郷の村が大火に見舞われることがなければ、彼の母は東京に育つこともなく、そこで父と出会うこともなく、あなたのようなかわいい初孫が生まれることもなかった、といった話だった。
その話の枝葉として、村の外れで、祖父と花の種を撒いた記憶が語られた。いつの出来事かはわからないが、おそらくは、火災の前のことだろう。大変なことがあった後で、そんな余裕があるとは思えない……。
この話と、現像された写真にあらわれた景色が、記憶のなかで結びついた。
この写真は、祖父母が撒いた種によってできた花畑を撮影したものなのだ。
そして、その花言葉が〈希望〉であるはずだった。というのも、祖母はかつて祖父からそのことを聞き、たいへん感心したというから。
しかしいま花言葉を調べると、〈希望〉ではないのだった。
つまり祖父は、祖母に偽りの花言葉を教えたか、それとも花言葉を知らずに放言したか、あるいは単純に勘違いをしていたことになる。
記憶のなかに橙色の疑問が揺れている。
玲二は窓外を見やった。新幹線は長野の街に入りつつあった。早回しの人生がいくつも通り過ぎた。景色を楽しみつつ、玲二は考えた。
――まあ、べつに〈希望〉であってもいいだろう。
ある人間が花を見て、その花に言葉を当てはめることに、正答も誤答もない。
フィルムにしても、そうなのだ。どんな瞬間でも、好きなように切り取ることができる。暗くしたり、明るくしたりして、随意に表現できる。
この流れゆく景色だって、シャッタースピードを速めて撮れば、完全な静止画があらわれて、思いもよらなかったものが見えてくるだろう。
たとえ表現されたもののもつ意味が、事実とまったく正反対だったとしても、それはそれでかまわない。
マンマの言うとおり――すべての写真は、それ自体では真実なのだ。
そこまで考えて、玲二は直感的に、祖父が嘘をついたのだと知った。
顔も知らぬ祖父の気配が、理路の道筋に残っていた。
この嘘は、彼らにとって必要なものだったのだ。
手に土をつけて花の種をまいていたときの、彼らにとっての花言葉が、〈希望〉だった。どんな理由であったのかは、わからないが――そのときの彼らの未来に〈希望〉が必要だったのだ。
駅前の蕎麦屋で腹ごなしをしたあと、店の主人に村の場所を尋ねた。釣り銭を数えていた店主は首をひねり、青垣村のことかと、玲二が覚えていたのとは違う発音でつぶやいた。
「ずいぶん昔に大火で焼けた村だ。山に囲われていて、奇麗なところだった。どんな用事だい?」
「祖母の故郷なんです。彼女のために、写真を撮りに」玲二はカメラを掲げた。
主人は頷いた。
「古いトンネルのむこうにある。地図を書いてあげよう」
駅前からバスに乗り、山間の奥深いところで降り、しばらく歩いてトンネルを見つけた。山の緑に覆われ、雨風に洗われたトンネルの壁は、染みだした地下水で濡れていた。歩道と呼べるものはなく、幅は車一台が通れるかどうか。のぞき込んだ奥のほうにまち針の頭のような光がなければ、入ることをためらっていただろう。
中程まで進むと、氷室になっているらしい、冬が戻ったみたいに冷えた。思いのほか長く、暗かった。出口の光で目が眩んできた。立ち止まり、目玉を瞼の上から指で押した。瞬きをしながらトンネルを抜けると、日差しが彼を照らした。
トンネルからつづく道はあるところで果てて、土と草に変わった。線の切れた木製の電柱の連続が導だった。臑で草を分けて進む、道とも言えぬ道の、両脇の野原が段々になっているのは、かつてそこに田畑があったからだろう。揚雲雀が舞い、空はみずいろ、山々は誰かの夢のなかのように青かった。百年来ずっと変わらぬ虫の音があった。姿の見えない鳥が鳴き、風が吹いた。
玲二は廃村に着いた。
ここに来た目的を忘れて撮った。あらゆる角度が興趣を惹いた。とくに高原を背景にしてみると、シャッターを切りながら、この世のものではない写真ができるのがわかった。崩れた瓦屋根の隙間、倒れた木製の電柱、遺跡のような石の垣根を、したたかな自然が草花で飾っていた。あらゆる隆起や角度が美しさを惜しみなく与えた。祖父母が去ってから、ここでは密かな祝宴がずっと続いていたのだ。
まったくの偶然だが、寝転がってレンズをのぞき込み、絞りを合わせているとき、完璧な被写界深度で雀が画面の中央に来た。かつての村のなかで踊り続けているうちに日が傾いてきて、それで新しい顔が見えた。
俯瞰を撮ろうと駆け上がっていった丘の上に、オレンジ色の花が一面に、風に揺れていた。
彼は目を凝らして丘の形を把握し、あたりを歩き回って、あるところで歩みを止めた。ポケットから写真を取りだして構図を確かめ、画角を切り替えてファインダーをのぞき込んだとき、忘却の淵からひとつの記憶が救い出された。
玲二は家に帰り、その写真を印刷した。それ自体はうまく表現されていたが、年代物のフィルムの質感ではなかった。コンピュータでデジタル・データを読み込み、彩度を落とし、階調の量を引き下げた。記憶を頼りに印刷を繰り返すと、ある時代のフィルムが持っている、どこか懐かしい質感が再現されてきた。
玲二は無言のままその写真をしばらく眺めたあと、立ち上がって、別室で伏せている祖母のもとに来た。
「写真ができたよ」と玲二は言った。
祖母はうすく目を開き、震える手で受け取り、一瞬とも永遠ともつかないあいだ、写真を見た。
この世のものとは思われない花畑がそこにあった。その景色に、玲二によく似た男の姿をだぶらせて、薄く開かれた目の、しわだらけの目尻に涙が光った。